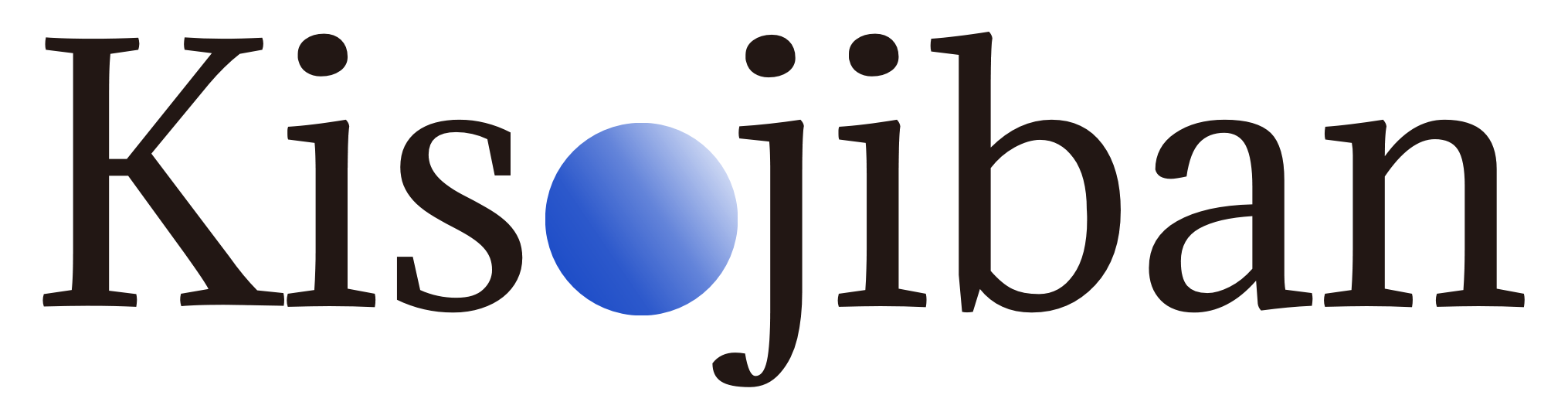「今日はよろしくお願いします。まずはみなさんの所属するグリーンプロジェクト事業部 について教えてください」
野仲
「東日本大震災以降、国内の再生エネルギー導入に対するニーズが高まりました。わたしたちの会社も、基幹技術を活かすかたちで、地熱発電事業を中心に調査・開発を推進し、また、脱炭素化の流れを受け、カーボンニュートラル事業にも取り組んでいます。グリーンプロジェクトは、新事業開発部として、環境問題などの新分野へ積極的に挑戦しつつ、基幹事業との連携・協力体制を構築しながら、新たなビジネスモデルの創出を目指すための部署です」
大西
「2022年に発足した新しいプロジェクトなので、最初は何をやったらいいのか、どこから手を付けていいのか、手探りの状態でしたが、まずは自分たちのできることをやろう、そし てそれを会社の未来へなんとなくでいいから繋げていこう、そんな気になってやっとスムーズ に動けるようになってきました。わたしは、大学ではこの会社の基幹業務である地盤解析の研 究をしていましたので、早い時期に新事業に関わることになり多少のとまどいもありました が、『まちづくり』にも関心があるので、地盤研究や防災への知見を活かし、この事業に携わっていけたらなと思っています」
今城
「わたし自身もまだこの仕事を始めて1年なので、なかなか全体の業務を完璧に理解するところまではいきませんが、いまの時代に合わせた、あるいはこれからさらに注目を浴びていく分野の活動をしていく重要なプロジェクトだと理解しています。大学では、環境社会学のようなことをやっていたので、いまの仕事にうまくいかせていければいいなと思っています」
「環境問題は間口も広く、とらえどころのない印象もありますが、みなさんは環境問題にどのように向き合っていらっしゃいますか?」
野仲
「そうですね。持続可能な世の中を目指すと言っても、社会からの捉えられ方も限りなく広くなってしまっているので、少し整理が必要なのかなと思います。グリーンプロジェクト自体は、わたしたちの持つ技術をいかしながらどういった分野で環境関連の仕事をしていけるかを、試行錯誤しながら進んでいるところです。個人レベルで言えば、わたしは学生のときから火山の研究をしているので、地球温暖化を防ぐための再生可能エネルギーとして『地熱』を活用することを、世間一般に広く知ってもらいたいと思っています」

大西
「たしかに、わたしたちが考えていかなければならない環境問題の範囲は大きいのかもしれません。ですが、これまで会社が積み重ねてきた知や技術をどのようなかたちで社会に還元していけるのかを突き詰めていくと、自ずと範囲も狭まるのではないかと思います」
今城
「わたしは環境問題に取り組むのがすごく楽しいんですよ。ですが、就職活動を通して、環境問題の解決と利益を追求することを両立する仕事につくことは難しいと感じたこともあります。最近は各企業の意識がものすごく変わってきています。その変化を仕事のなかで、肌で感じられるのが、とても興味深いです」
「環境問題は個人の意識も大事だと思いますが、組織だからこそ取り組めることもあると思います。個人にしかできないこと、企業にしかできないこと。そのあたりのみなさんの意識について教えていただけますか?」
今城
「やっぱり個人の問題としては、ゴミの分別など身近に実施できることが基本なんでしょうね。個人個人の環境問題に対する行動や思いを、積み重ねることで解決につながると思います。組織としては、自治体さんとのお付き合いのなかで、国の方針と、現場の体制のギャップを埋めるために、環境問題に対する考え方やアプローチの仕方を軌道修正し、事業の計画段階で少しでもいい影響を与えていく。僭越な言い方ですが、そういう『環境全般に対する啓蒙活動』が、組織としてのいまのわたしたちの役目なのかなと実感しています」
大西
「国が旗振り役をやることに対し、より具体的な設計図を描くことがわたしたちの仕事と言えるかもしれないですね。そのためには、広い知識も必要になるし、深い追及の姿勢も必要となります。個人の取組みの中で私が面白いと感じているのは、環境省「ゼロカーボンアクション30」に掲載されている「今持っている服を長く大切に着る」です。衣服の購入量を1/4にすると年間194kgものCO2削減に繋がるようなので、おしゃれのために服を買い替えたい気持ちを少し我慢して、長く着られる服を大切にしなきゃ、と(笑)」

野仲
「わたしは地熱構造モデルの推定をやっているときが無性に楽しい。大学にいたときからずっと研究していることなので、現地調査で、目をつけていたところから温泉が湧き出しているのを確認できた瞬間など、いまだにものすごくワクワクします」
大西・今城
「へえ、そうなんですね(笑)」
野仲
「ちょっと説明させていただきますと、地熱資源開発の進め方は、主に地熱構造の3要素 (貯留、流体、熱構造)、どこに蒸気や熱水が眠っているか、蒸気がどこから出るかなど、い ろいろなデータから調査します。そこで得られた知見を元に、地熱構造モデルというものを作 成し、推定される資源量から事業性を評価していくことになります。個人的にはもっぱら楽し い作業なのですが、いちばん大事なことは、この開発への地域の人の理解を得ることなんで す。発電を考える際も余剰熱の再利用をご提案し、環境への負荷を少しでも減らす方向へ導い ていく。実際に、計画段階のものもありますが、魚の養殖や雪道の溶解、バナナの栽培などに、地熱が積極的に活用されています。ちょっと手前味噌になり ますが、こういう個々人の研究に組織の力を結集させることによって、大きなちからとして社 会のあり方を変えていく。そんな正の連鎖みたいなものが生まれてくるのが理想かなと思っています」
「国は来る2050年をカーボンニュートラルのひとつの目標地点としています。そのころ出現する『未来の街』はどのようになっていると思いますか? みなさんの意見を聞かせてください。
野仲
「そうですね、エネルギーの問題だけで言うと、残念ながらそう楽観的には想像できないかもしれません。やはり、圧倒的にエネルギーが足りない。地熱発電などは、やはり火山のある場所に限られてしまう。先日、マイクロプラスティック(微細で有害なプラスティックごみ)が大気中に出始めてしまうとニュースを見たのですが、そうなるとマスクなしでは生活できなくなる。そんな悲観的な未来もじゅうぶんにありうるわけです。もちろん、そうならないためにいろいろな組織が力を合わせてがんばっていかなければならない。足りていないからやる意味がないというのではなく、太陽光発電などとも合わせて、少しでも地球環境にやさしい状況を作ることができれば、それはじゅうぶんに意義のあることだと思います。」

今城
「わたしは、良くも悪くもけっこう大きく変わるのではないかと思うんですよ。いまも自治体さんとのお付き合いなかで、まちが少しずつ変わってきているのを感じます。ただ一方で、急激な人口減少や地方都市の過疎化は深刻で、自分たちの計画する『未来のまち』と『現実社会の変化』との落差をどう埋めるのかがこれまた一苦労で、いろいろなことが間に合うのか間に合わないのか」
大西
「残された25年が長いのか短いのか、正直想像できないですね。やはり自分ひとりで考えるには限界があるので、国の施策や専門家の意見などをうまく取り入れながら、集合体として目標の実現に向かっていくことが重要だと考えています」
「では、その2050年、みなさんはどんな街に住んでいたいですか?」
野仲
「2050年って、65歳か」
大西・今城
「立派なおじいちゃんじゃないですか(笑)」
野仲
「だよね」
大西
「若者にやさしくされて生きていたいですね(笑)」
今城
「ですよね。環境問題の先駆者として尊敬を集めていればやさしくしてもらえるのかも (笑)」
野仲
「やはり25年後は、少しでも自然災害が少ない街に住んでいたいですね。電力もじゅうぶんに足りて、もう環境問題そのものを考えなくてもいいような時代になればいい」
大西
「個人的には『地産地消』が未来のまちづくりの基本だと思います。自分の住んでいる場所 で食料やエネルギーを生産し、災害が起きてもなるべく近隣のバックアップ施設で代替していけるような、そういうコンパクトで強靭なまちができるといいなと思います」
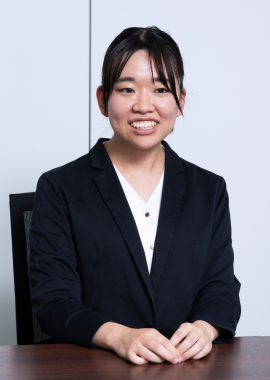
今城
「逆説的な言い方になりますが、2050年の未来になったときに、あのとき(25年前に) わたしたちが対処をしていなかったから、わたしたちが課題を残してしまったからこうなってしまった、そんな街にはしたくない。ですから、問題を先取り先取りで対処していかなければ、という思いがあります。現在グリーンプロジェクトは、再エネ、防災・減災、脱炭素、環境保全など地域の課題解決に繋がる幅広い分野の事業を検討しています。災害に強く、地域住民が暮らしやすい循環型の街づくりというのが一番大きな目標です。 未来の暮らしのために最先端のことを追求していくのはやりがいですけど、不確実性も高く、かたちにしていくのにまだまだ力不足、そういうもどかしさのなかでがんばっています。(みんなの顔を見ながら)ですよね?(笑)」
野仲・大西
「はい、がんばっています(笑)」
「新たにどんな人に仲間に加わってもらいたいと思いますか?」
大西
「基礎地盤コンサルタンツは、名前からわかるように『地盤』で全国を支えているので、土や地面に少しでもロマンを感じられる人ならどんどん入ってきてほしいなと思います。このグリーンプロジェクトは、未来に向けた視野の広い仕事なので、バラエティ豊かなスタッフがいてちょうどいい。どんな人でもきっと戦力になります」
今城
「そうですよね。新事業を目指しているので、新しい考え方を引っ張ってこられる人が入ってくれると頼もしいですよね。たとえば、夢がある人。将来の課題解決に向け、広い視野の方に来ていただけるとうれしいです」
野仲
「未来につながる理想的な都市づくりをぜひいっしょにやっていきましょう。わたしは山登りをするのですが、少しずつ地道に山頂を目指して登っていく感覚と、地道に調査を重ねながら街づくりを進めていく感覚はどこか共通していると思います。山好きの人が来てくれるとうれしいなあ」
大西
「温泉を発見して、いっしょにワクワクもできますしね!」

グリーンプロジェクト事業部のみなさん
(情報、肩書等は 2023 年 6 月取材時のものです)