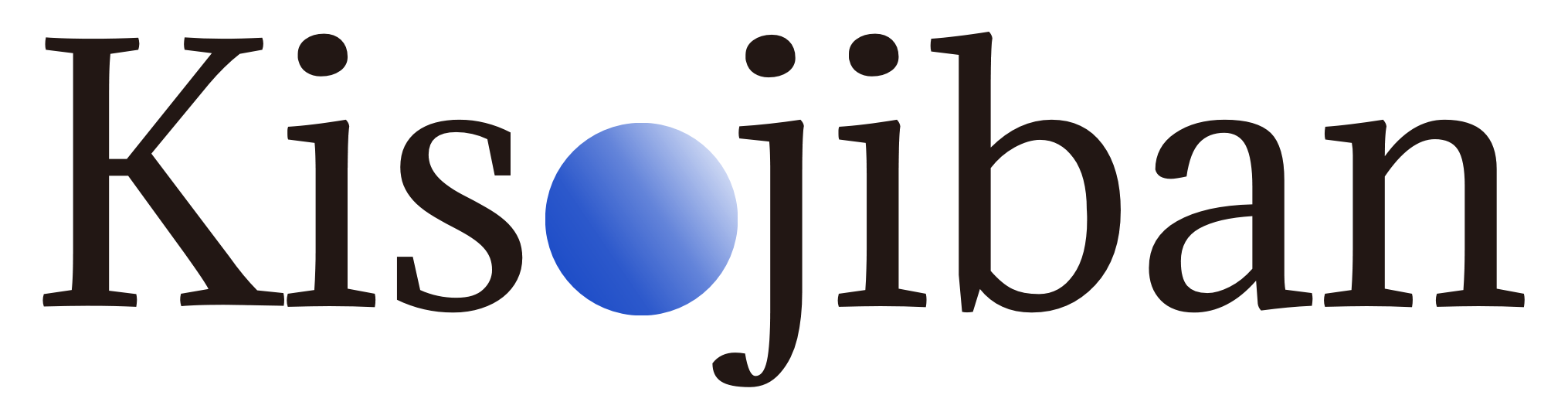安田進先生のインタビュー記事が新聞に掲載されました /地盤災害を未然に防ぐためにやるべきこと
プレスリリース
建設通信新聞2018年7月20日【16面】地盤特集(4) 掲載より
◎地盤災害を未然に防ぐためにやるべきこと
【土木の視点/東京電機大学レジリエントスマートシティ研究所 プロジェクト研究教授 安田進氏に聞く/排水管埋め液状化防止/大規模地震発生に備え対策急務

地盤と一言で言っても、(a)構造物を支える地盤(b)構造物の基礎(c)土構造物(d)地中構造物(e)自然斜面--と扱う範囲は多義にわたっていま す。ただ、地盤における地震対策については、まだ年月が経っていないため、耐震設計や対策方法、進捗状況が大きく異なり、まだ万全とは言えない状況です。
過去、地震によって課題とされてきた点は、(1)液状化(2)自然斜面の崩壊(3)盛土造成地の被害(4)土構造物の被害(5)地中構造物の被害--が挙げられます。
(1)液状化
液状化の発生頻度は高く、1年半-2年に1回のペースで被害が出ています。
特に1964年の新潟地震で、液状化によってマンションが倒壊することで大きくクローズアップされました。
その後、対策の必要性が認識され技術の開発が進められたものの、95年の兵庫県南部地震では、岸壁・護岸背後地盤の流動化によって杭が破壊されるなど大きな被害が発生しました。その後も2011年の東北地方太平洋沖地震によって、 東北から関東までの広範囲で液状化が発生し、市街地に深刻な被害を与え、現在も復興に向けて対策が行われているところです。

開削工法により排水管を敷設(神栖市)
地下水位低下工法は有効
市街地が広範囲に液状化被害を受けた茨城県の潮来市・神栖市・鹿嶋市・東海村、千葉市、埼玉県久喜市では、地下水位低下工法が採用されました。研究や技術開発が進み、道路の地下3m程度のところに排水管や浅井戸を埋めることで液状化を防げることが分かりました。施工範囲が民地にかからないため対策しやすいというメリットがありますし、何よりコストがあまりかかりません。住民の財産を守るためにも有効な手段といえます。地盤条件にもよりますが、有効であると判断された場合は導入しても良いのではないでしょうか。

東北地方太平洋沖地震による仙台市青葉区折立5丁目の盛土造成住宅地の被害
(2)自然斜面の崩壊
1978年の伊豆大島近海地震では、道路斜面約800カ所が被害を受けました。そのことがきっかけとなって研究が始められ点検方法の検討が始まりましたが、一般道路は路線延長が非常に長く、地盤調査も行われていないため、危険であると考えられる個所では路線の場所を変更することも必要であると考えます。いまもなお、地震だけではなく大雨によっても崩落が発生し道路や鉄道、宅地に被害を及ぼしています。最近では、大分県中津市耶馬渓町で降雨や地震がなかったにもかかわらず突然崩落し6人が亡くなったのは記憶に新しいと思います。また、2004年の新潟県中越地震では、新潟県山古志村で河道閉塞し土砂ダムが発生しました。

駿河湾地震による東名高速道路の盛土被害
(3)盛土造成地の被害
1960年代から都市近郊の丘陵・大地で大規模な宅地開発が進められました。当時は宅地造成等規制法(宅造法)が施行されましたが、耐震対策が盛り込まれていなかったため、最近、被害が急増しています。横浜市や川崎市では、人口の急増によって開発が進んだ結果、危険な土地(家屋を含む)が数多く存在します。宅造法が改正されたことで、大規模盛土造成宅地の分布状況を調査、危険と判断した個所においては必要な措置を講じなくてはいけません。現在、擁壁がずれているなどの目に見える危険個所から順次、調査が行われています。

既設河川堤防の液状化対策として地盤改良を行っている
(4)土構造物の被害
2010年に発生した駿河湾の地震によって東名高速道路の片側車線が崩れました。原因は盛土材として使った泥岩塊の風化(スレーキング)によるものでした。そういったことがきっかけとなり、道路では点検・調査のマニュアルを作成したほか、東海道新幹線でも点検・対策が行われています。
一方、河川堤防では、1995年の兵庫県南部地震によって淀川堤防が被害を受けた後は、耐震点検や補強が順次行われました。しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震では、国直轄の河川堤防で多くの被害が発生、関東地方整備局では939カ所で被害を受け、そのうち55カ所の大規模被災個所で地質調査が行われたところ51カ所は液状化による被害であると報告されています。現在、考えられている既設堤防の対策としては、締め固め対策、固化対策、矢板対策、水位低下対策などを採用しており、耐震点検や地震対策が積極的に行われています。
(5)地中構造物の被害
地震によって、マンホールの浮き上がりが発生したのを受け、対策が始まりました。埋め戻し土に砂を使用しかつ地下水位が高い場合、浮き上がる可能性が高いことから対策が必要となります。これに対し、東北地方太平洋沖地震の際、東京湾岸の埋立地などでは異なった被害が発生しました。埋め戻し土だけでなく地盤全体が広範囲で液状化し、さらに継続時間が長かったため、液状化した地盤が大きく揺すられ続ける揺動現象が生じ、マンホールのずれや管渠の継手の抜けなどが発生しました。そこに土砂が流入したため、浮き上がらずマンホールや管渠に土砂がつまる被害が生じました。
液状化した地盤で揺動現象が生じると、路面がゆっくりと波打つため、堅い面からの跳ね返った波と液状化の波とがぶつかり合い路面が突き上げられ、盛り上がる場合があります。万が一大きな地震が発生した場合、暗くなると路面の状況が分かりにくいので車等で走行する場合は、このような揺動現象による路面の変状や、前述したマンホールの浮き上がりに十分注意する必要があります。
相次ぐ地震、対策は必須
6月18日に大阪北部地震が発生しました。火災やブロック塀の倒壊など被害が発生しましたが、今後、ほかにも大きな地震が発生する可能性が十分にあります。政府の地震調査委員会から今後30年以内に震度6弱以上の大地震が発生する確率を示した18年版『全国地震動予測地図』が公表されましたが、3大都市圏を始め、四国の太平洋側で高いとされています。大規模地震が発生した際に被害を受けないためにも、研究を重ね、対策を行うなどして備える必要があります。
Copyright ©2012-2018 The Kensetsutsushin Shimbun Corporation.